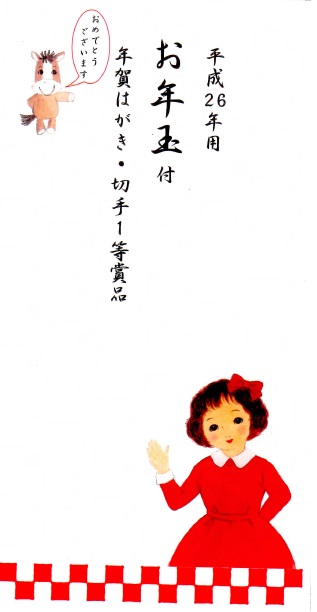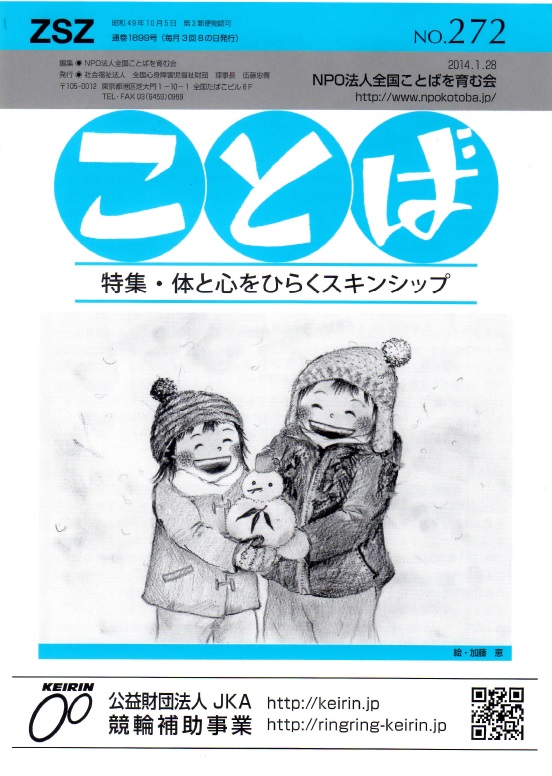2014年3月12日
「病床転換型居住施設」に反対する声明
特定非営利活動法人 日本障害者協議会
2014年、日本も障害者権利条約(以下、権利条約)の締約国となりました。この何年かをふり返ると、
その条約締約のために障害者基本法を改正し、分け隔てのない社会の実現の重要性が明確にされ、
障害者差別解消法も成立しました。
そのような中、現在、精神科病院の社会的入院の解決の方便として、「病床転換型居住施設」即ち、
精神科病院の中に”住まい”を取り込もうとする政策が議論されていることに強く異議を表明します。
精神障害者の多くが、いまだ根強い社会の偏見や差別の中で、住むところや働く場を得ることが
困難な現状にあり、30万人以上の人たちが精神科病院の中で非人間的な状況に押しやられています。
精神科病院内には行動制限最小化委員会が増えているにも関わらず、隔離・身体拘束はむしろ増加傾向にあるのです。
その上、「病床転換型居住施設」という病床の看板のすげ替えに過ぎない、真の地域移行とはかけ離れた病院への囲い込みの政策が、厚生労働省の検討会や社会保障審議会障害者部会で「地域移行」の一つのあり方として議論されていることに、違和感を禁じ得ません。
「病床転換型居住施設」の是非についての議論を閉ざすべきではないという意見がありますが、地域資源や地域サービスが絶対的に不足する中で検討が行われた場合、結論が一定の方向に導かれるものとなることは明白です。「病室で一生を終えるより、病院内であっても自分の部屋を持って一生を終えた方がマシ」という検討会での発言を肯定する向きもありますが、これは現状と乖離した、甚だしく差別的な考え方でありましょう。
さらに、障害者政策委員会でも指摘されたように、病院内で生活が完結することが容易に推測され、これは精神障害者を「二級市民」と見なし差別的に扱うものであり、差別解消法や障害者基本法等の目的にも明らかに反するものです。
この病床転換型居住施設提案の背景には、社会的入院の解消が思うように進まないこと、一方で、精神科病院の経営問題があることは明らかです。しかし、権利条約を批准した今日では、精神障害者の人権が守られ、インクルーシブ社会に向けた政策が推進されなければなりません。
また、精神科病院入院患者の意向を調査した上で、この制度を導入するという意見があります。しかし、長年社会的入院を強いられてきた当事者に対し、唐突に意向を聞いても、情報が圧倒的に不足している 状況で、的確な意思表明をすることは困難です。それでも敢えて意向を聞くのであれば、望めば退院後 の生活を支える条件を示して聞くべきです。現に、精神保健福祉法第一条(目的)には「障害者総合支援法 と相まって」と明記されているのです。
権利条約の締約国となった今、日本の精神保健福祉政策は、社会環境や法制度、社会サービスのすべてに障害者の人権の確保と尊厳の尊重の原則を取り入れ、政策決定の過程に当事者参画が保障される方向へと切り替えていくべきです。また、そのための住宅や相談や介助など、必要な社会資源の整備は緊急の課題です。
権利条約は、「他の者との平等を基礎にして」を謳い、「特定の生活様式(施設)で生活する義務を負わないこと」を高らかに宣言しています。このようなインクルーシブの理念に逆行する動きは、絶対に許すことはできません。
日本障害者協議会は、以下のような重大な問題を孕み、障害者権利条約の理念と条文に逆行する「病床転換型居住施設」に強く反対します。
記
1. 病床転換型居住施設は、障害者権利条約の理念や条文に直接違反しているばかりか、障害者基本法第一条(目的)、第三条(地域社会における共生等)及びそれを受けてつくられた障害者基本計画に反しているので絶対に認められない。
2.現在、精神科病床・病棟の多くは街中から離れていたり、閉鎖的な環境のまま、呼称だけ病床から住居に変えても地域移行とは言えない。患者自身が、退院し、地域で暮らしている、という実感は持てない。さらに真の地域移行に向けて努力してきた患者・関係者の取り組みを妨げることになる。
3.病床転換型居住施設が実行されれば、病院及び施設に居住する精神障害者が隔離され続ける。これは問題の本質的な解決にはならず、断じて地域社会での共生とはならない。
4.病床転換後の居住施設が個人の住まいではなく、入所施設、介護施設として運用されれば、門限になったら鍵を掛ける等の管理的運用が予想され、直接的な人権侵害になりかねない。
5.病床削減による精神科病院の減収を精神障害者の地域生活を犠牲にして補おうとするのは、精神障害者の人権(地域移行の権利)を侵す行為であり、日本国憲法にも抵触する。
6.居住施設を設置し運営することは、本来的に医療の役割ではなく、精神科病院が行う必然性も正当性もない。
7.精神科病院は、他科の病院に比べ、医師、看護師などのスタッフの基準が低く、入院患者の多くは、劣悪な入院生活を強いられている。このこと自体が既に差別的取り扱いである。その上に居住施設を新設することは、そこに住まざるを得ない「二級市民」としての精神障害者を生み出し新たな障害者差別を積極的につくり出すことになる。