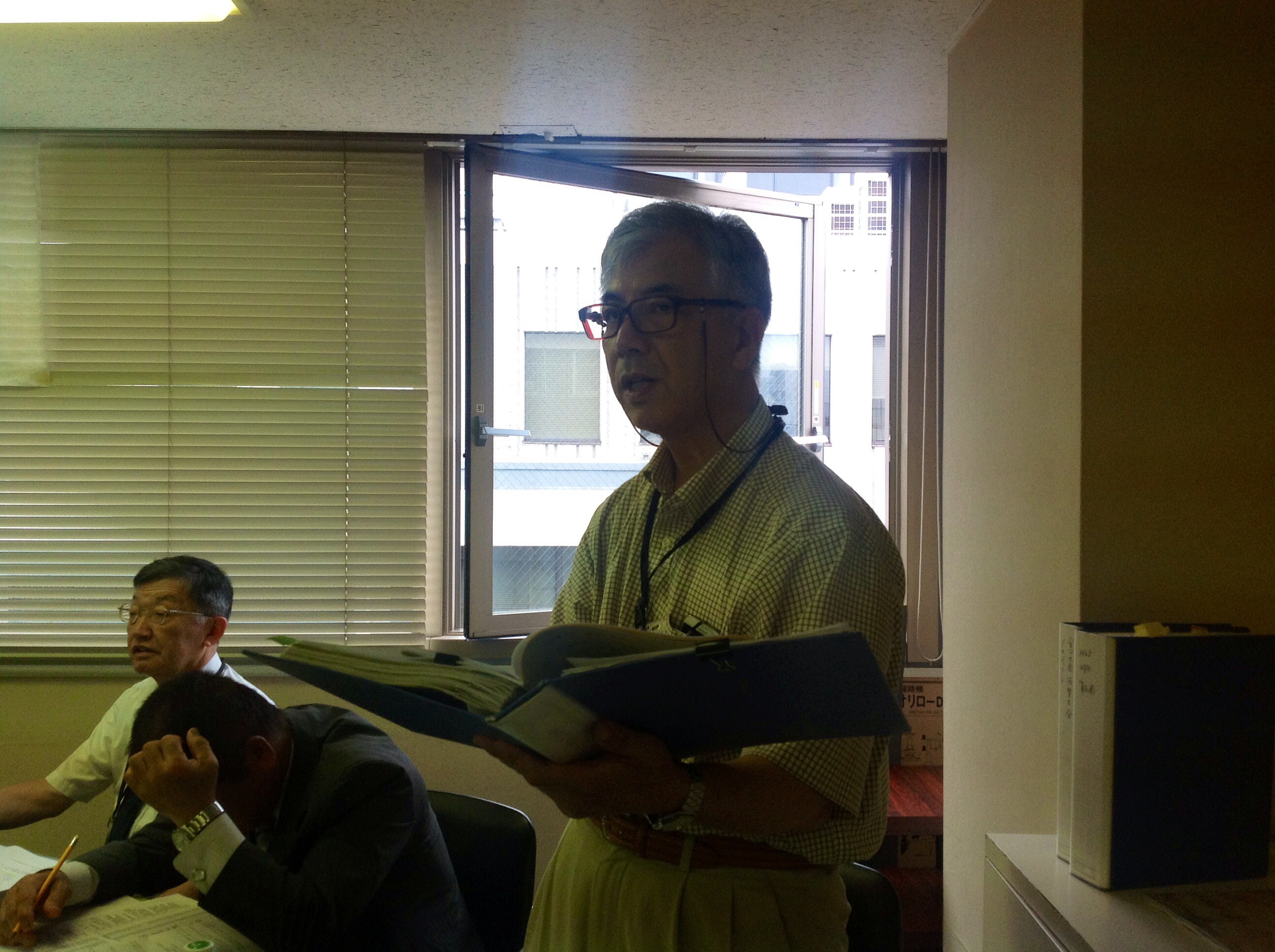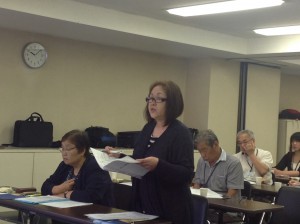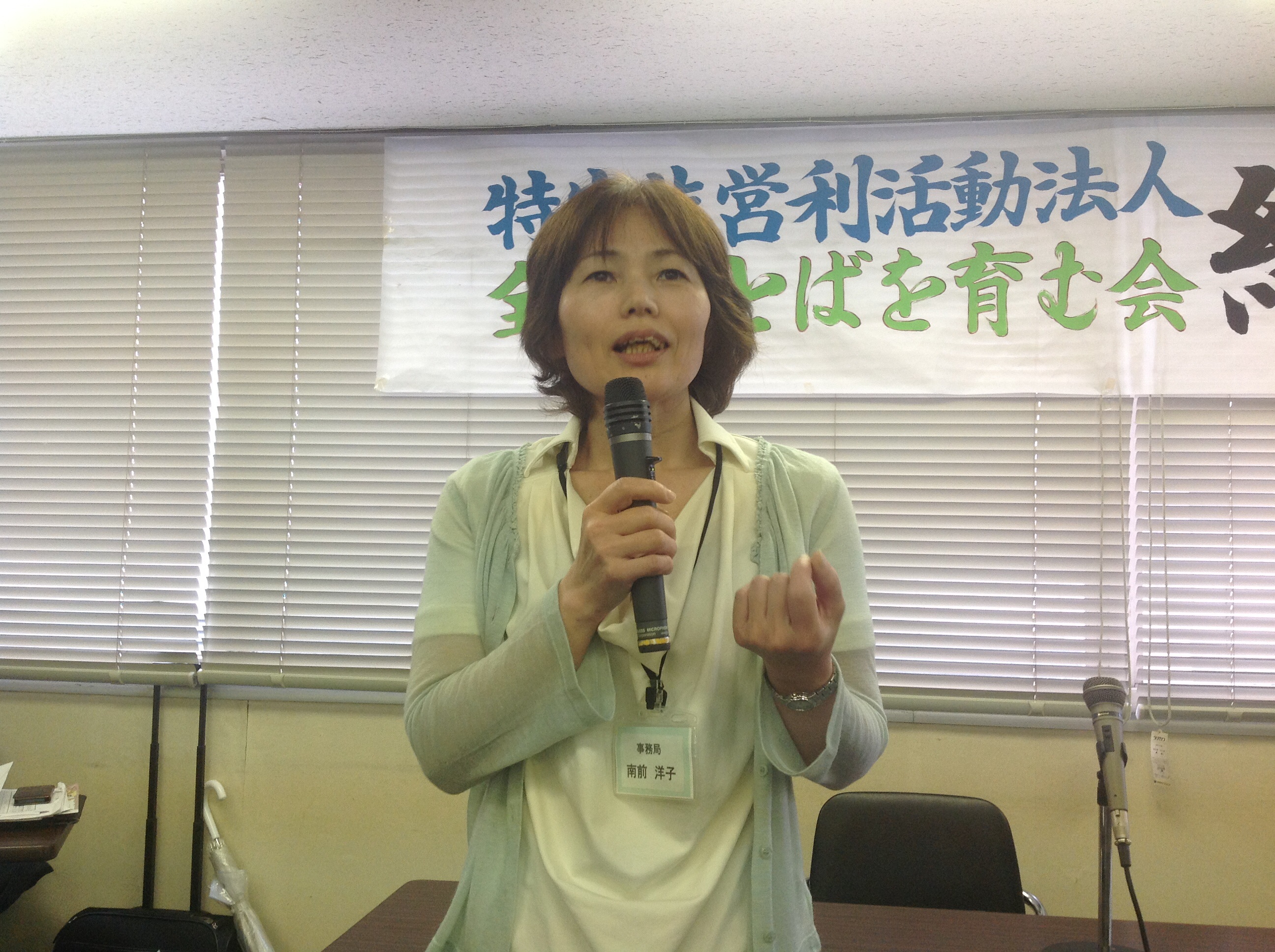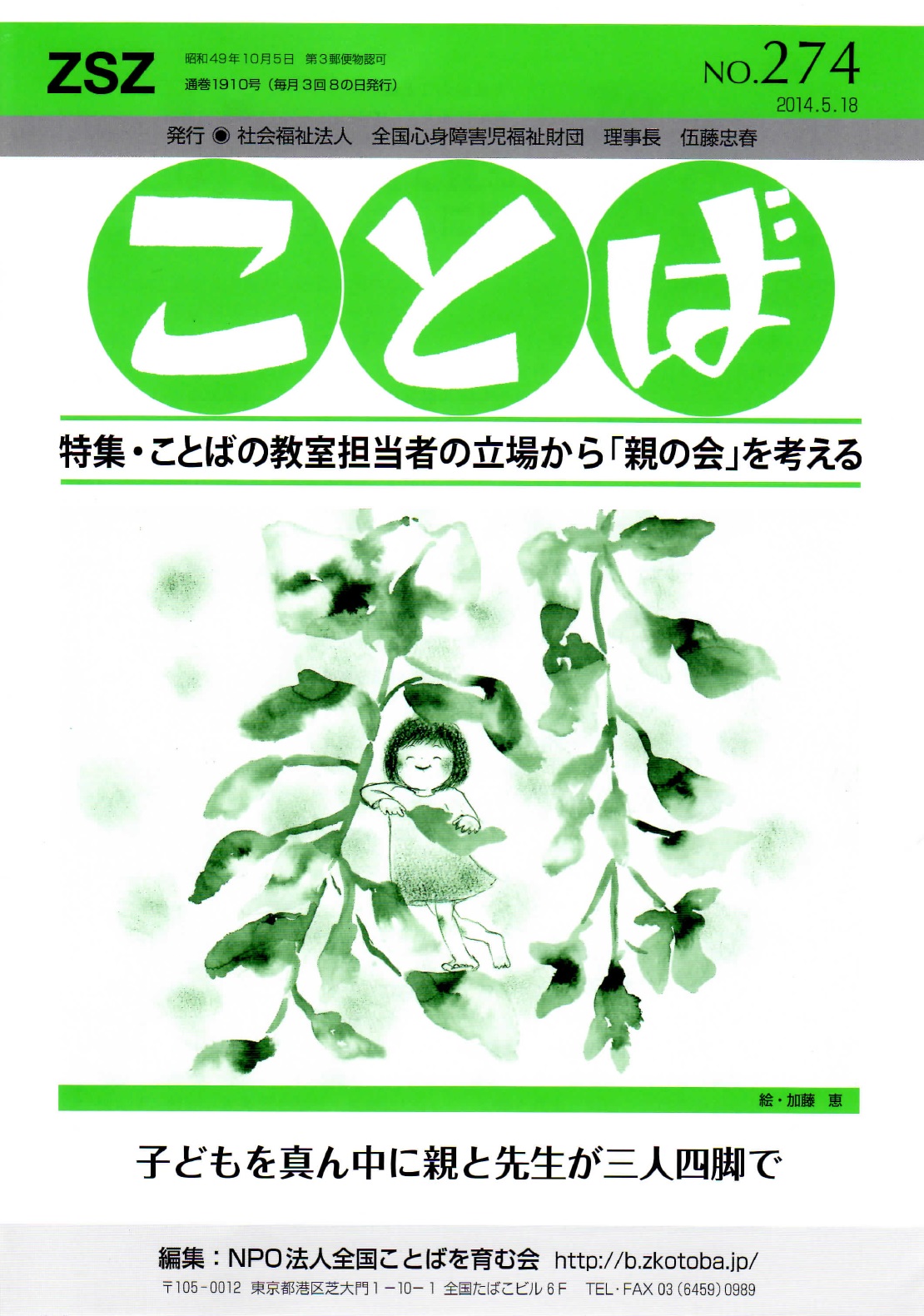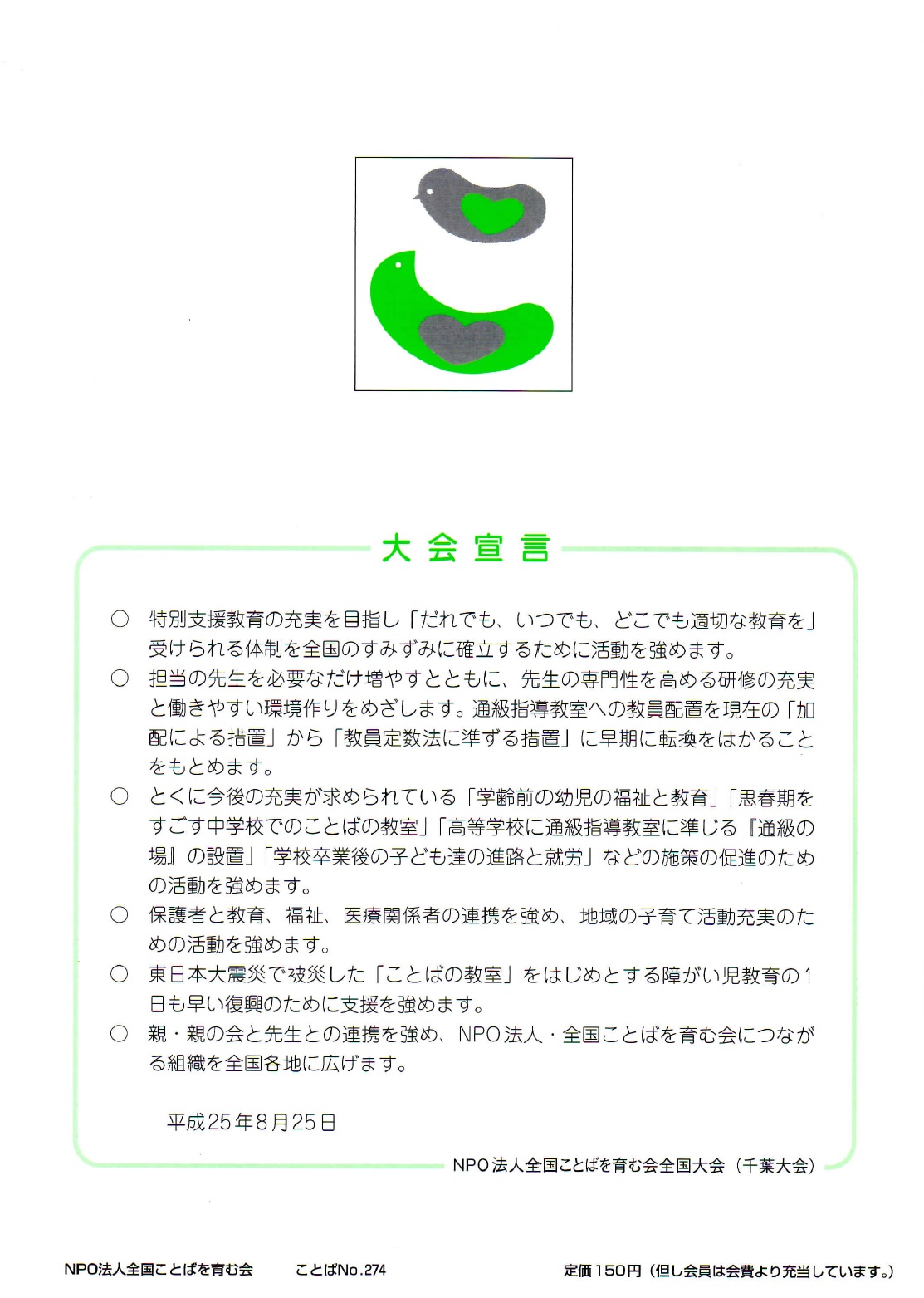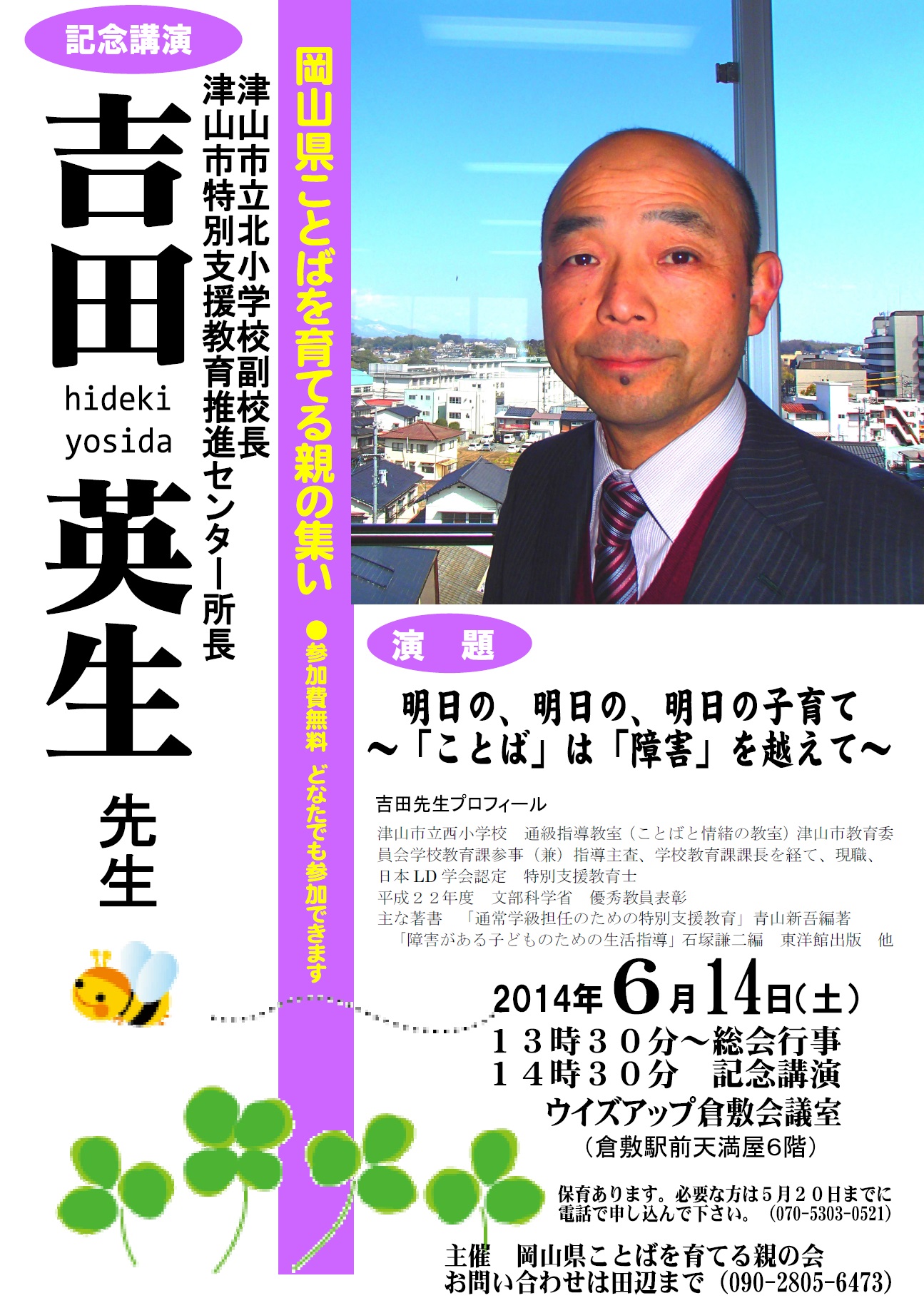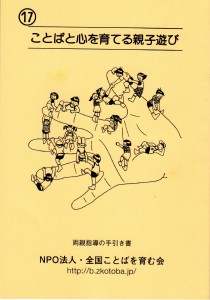○福島民友新聞 2014年6月8日 社説
障害者施設の休廃止/事業再開へ連携の輪広げよ
相双地方の障害者福祉サービス事業所70カ所のうち、震災と原発事故の影響などで4月1日現在、22カ所が廃止したり、休止していることが県のまとめで分かった。廃止は1割、休止は2割に上る。
休止、廃止施設のほとんどが原発事故の避難区域内にある。避難した障害者のため、避難先で運営の再開を目指しても、職員が別の場所に避難して施設を離れたケースもあり、新たな人材を確保することも難しいのが現状だ。職員の不足が休止、廃止の大きな原因となっている。
障害者にとって、慣れ親しんだ施設と、スタッフの存在は大きい。施設と求職者をつなぐ場を多く設けるなど官民が連携を強めながら人材確保を図り、施設の再開につなげてほしい。
施設を利用していた相双地区の障害者の中には、避難生活で症状が悪化したり、施設の休止や廃止で居場所をなくし、親ら家族と生活している人もいる。家族だけで支えることで、親らが体調を崩すなど、新たな問題も指摘されている。
事業所にとっても、避難先での再開は大きな決断だ。法律では、避難先で再開した施設は仮設の扱いで、避難指示解除後に原発事故前の場所で事業を再開する場合、避難先の施設は閉鎖しなければならないこともある。事業者が再開に踏み切れない理由の一つとも指摘されており、政府には柔軟な対応を求めたい。
他県に人材を求めても、応募者がいなかったケースもある。震災前、卒業生を県内の施設に送り出してきた県外の専門学校の中には、保護者の理解が得られないことを理由に応募を見送る学校も出ている。原発事故による風評が影響を与えているのであれば、正しい情報を発信することが重要だ。
新たな人材の確保は、一つの事業所の力では限りがある。身近な窓口となるハローワークをはじめ行政が人材確保のための周知に努め、障害者の居場所の確保と雇用の創出に力を入れてもらいたい。
避難先を将来にわたる拠点と決めて再出発した浪江町の事業所の代表者は「地域に支えられて再開することができた」と話す。福祉施設の在り方の根幹を示す言葉と言えるだろう。
人員不足が原因で運営を諦める事業者が出ないよう、行政と事業者が解決策を探り、地域も理解して人員の確保を進めてほしい。支援を必要とする障害者を孤立させ、新たな苦しみを与えることのないような取り組みを求めたい。